給付金と進次郎人気だけで自民党は選挙に勝てるつもりなのか 


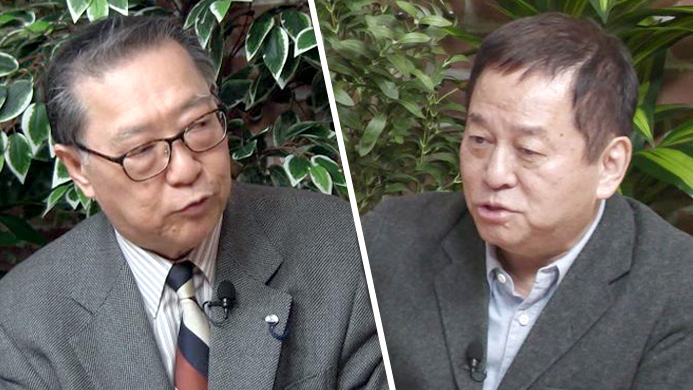
自公連立政権が少数与党に陥り、波乱の国会になることが予想されていたが、実際はごくごく平和裏に国会審議が進んでいる。ところが、日本から一歩外に目を向けると、世界はまさに激動のただ中にある。日本の永田町だけが世界から隔離された異次元空間のように見えてならない。
先週、トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領と電撃的に電話会談を行い、ウクライナ戦争の停戦に向けた交渉を開始することで合意したことが、ヨーロッパ諸国に衝撃を与えている。ヨーロッパの国々はどこもNATOという軍事同盟を通じてアメリカと連携することで、ロシアを押さえ込むことを安全保障政策の柱にしてきたが、アメリカがそのポジションを根底から覆しロシアと手を結ぼうということになってきたからだ。トランプ大統領が個人的に気脈を通じるプーチンとの間で「ディール」を成立させるようなことがあれば、第二次大戦後一貫してアメリカの後ろ盾を前提としてきたヨーロッパ諸国は安全保障政策を根底から見直すことを余儀なくされることになる。
翻って日本では今年度予算を巡り、高校授業料の無償化と所得税の控除枠の引き上げが目下、政治の最大の争点になっているという。無論、そうしたひとつひとつの政策を丁寧に審議し合意形成を図っていくことは政治の重要な機能だ。しかし、今の日本の政治が激変する国際情勢に本当に対応していけるのか、甚だ不安を抱かずにはいられない。先週以降、アメリカとロシアとウクライナ、そしてヨーロッパを舞台に起きている国際政治の激変が、東アジアには及ばないと考えるべき理由は何もない。
幕末に黒船が来航した時、長年太平の世に慣れきった「平和ボケ」の幕府の役人たちは右往左往するばかりで、誰一人として現実的な対応ができなかった。その結果、日本は欧米列強との間で関税自主権が認められていない不平等な条約を結ばされ、その後50年もの間、苦しまされることになる。
日本では先日の日米首脳会談は成功だったとされているようだが、トランプ大統領は首脳会談直後に鉄鋼とアルミニウムに対する関税の引き上げを決定し、続いて自動車に対しても25%の関税を検討していることを明らかにしている。日本の対米自動車輸出は対米輸出全体の3割を占める、日本にとっては最大の輸出製品だ。そこに25%の関税がかかろうものなら、日本経済は大打撃を受けることが必至だ。
安全保障面でも経済面でも、日本が今にも危機的な状況を迎える可能性が出ている時に、日本の政治だけがどこか別世界にいるような感覚を禁じ得ない。
日本の政治はなぜこうまで現実の世界と乖離してしまったのか。今の日本の政治、ひいては統治システムで、現在の厳しい国際環境を乗り切れるのか。政治ジャーナリストの角谷浩一とジャーナリストの神保哲生が議論した。


