5Gを巡る米中の覇権争いと日本の選択 
野村総研エグゼクティブ・エコノミスト




1975年埼玉県生まれ。98年中央大学商学部卒業。同年日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。日経トレンディ編集部を経て2003年よりフリー。著書に『ケータイ業界30兆円の行方 キャリア再編のシナリオ』。
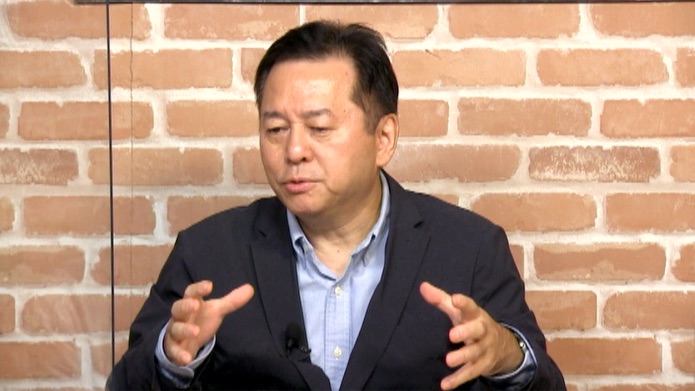
ファーウェイの孟晩舟CFOがカナダで逮捕されたことで、次世代通信規格の5Gが米中覇権争いの火種として注目を集めるなど、2019年は5Gの年になりそうな気配が濃厚だ。
高速大容量、超低遅延、多数端末接続という特徴を持つ5Gは、今年からアメリカなどで実用段階に入る。日本でも今年行われるラグビーのワールドカップの会場周辺で試験運用が始まり、2020年の東京五輪を目途にサービスが始まる予定だという。
移動体通信の規格は1980年代の1Gから最新の4Gまで、めざましい進歩を遂げてきた。通信速度もほぼ10年ごとに大幅な向上を続け、当初はテキストのやりとりだけで精一杯だった携帯電話を通じて、今やテレビと遜色のない画質の動画が見られるまでになっている。
ITジャーナリストの石川温氏は、これまでの移動体通信は人が使うことを前提としていたが、5Gからは機械同士がつながることが期待されている点が、最大の変化だと指摘する。
いわゆるIOT(Internet of things=モノのインターネット)の分野で、自動車や家電などがネットワークでつながることで、世界の産業構造が変わる可能性もあると石川氏は言う。
また、遅延がほとんどない5Gは、遠隔手術や離れたところから工事現場の重機を操作するなど、新たな用途も期待されている。
とはいえ、5Gで主に使われる28GHzの帯域は電波が遠くまで飛びにくく、通信障害も起こしやすいという弱点を持つため、これまで以上に多くのアンテナを必要とするなど、今後莫大な設備投資が求められる。今年中にサービスが始まるとしても、インフラが整い5Gがその本領を発揮するまでには、まだまだ相当の紆余曲折がありそうだ。
ITジャーナリストの石川氏に、5Gの画期性やその可能性について、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。