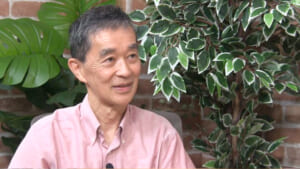たとえ茨の道でも気候危機に立ち向かう1.5度目標を堅持しなければならない 
地球環境戦略研究機関(IGES)気候変動ユニットリサーチディレクター


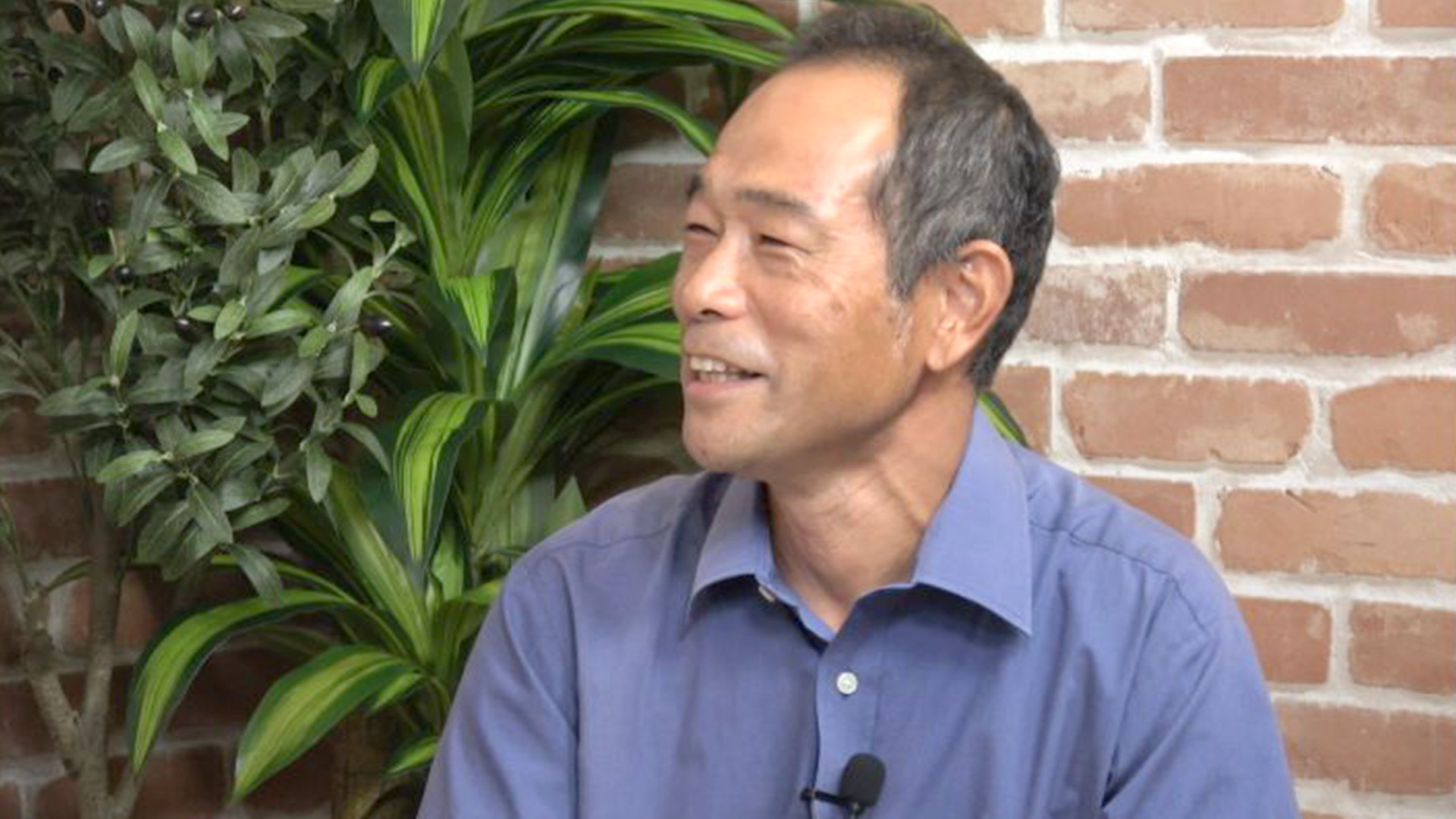
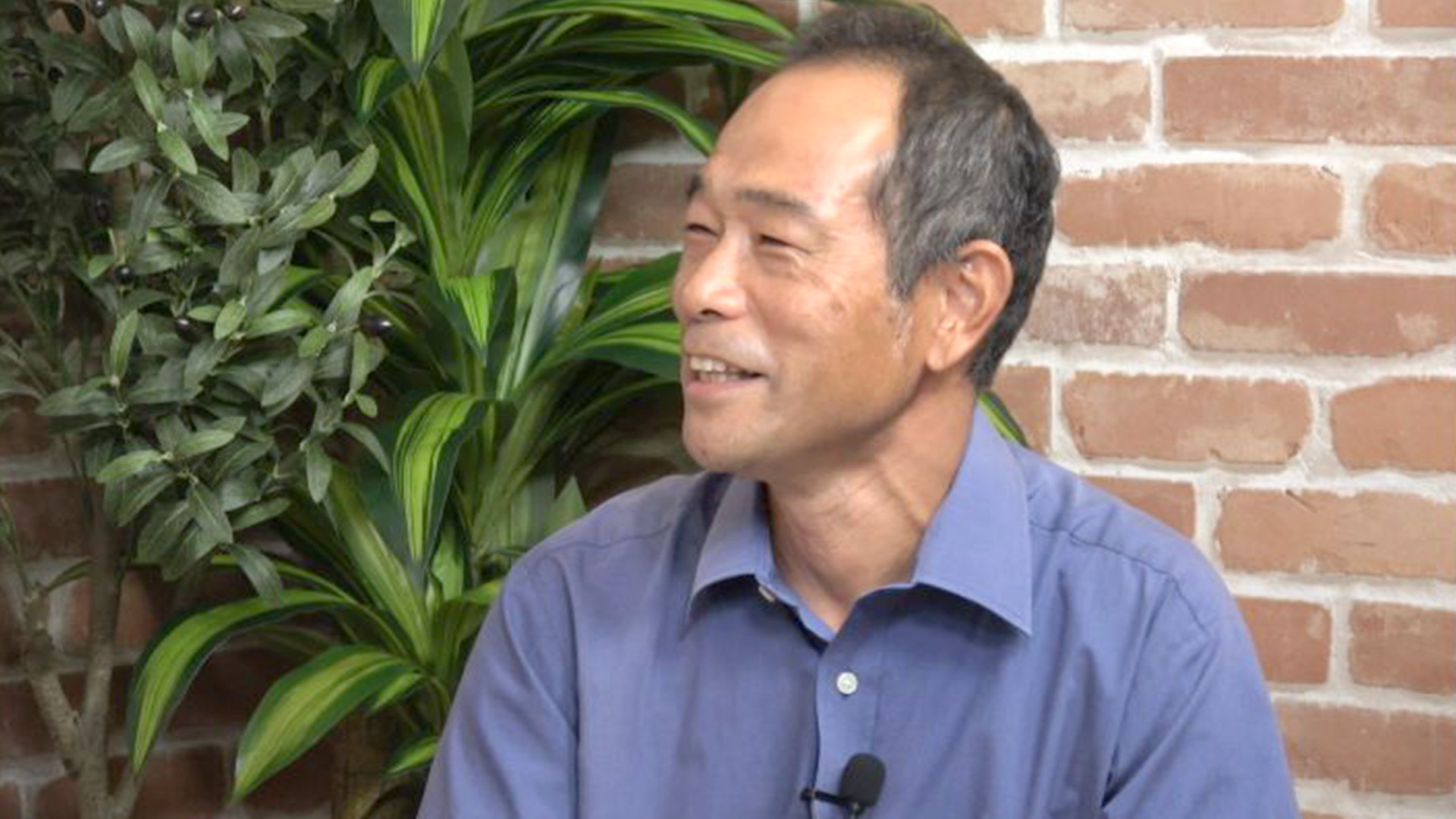
1972年東京都生まれ。99年東京農工大学農学部卒業。2003年東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士・技術士(環境)。自然環境研究センター学術研究員などを経て2008年より現職。2017年よりモニタリングサイト1000里地調査を担当。
今回の「セーブアース」では、日本自然保護協会の藤田卓氏をゲストに迎え、夏休みの大人向け自由研究として、「虫が減っているというのは本当か」をテーマに全国で行われている里地・里山の生物多様性モニタリング調査の結果を紹介した。
環境省が行っているこの調査は、全国約1,000カ所の里山や農地、湿地などを対象に、100年の長期にわたり生物の動向を記録していくというもので、2005年以来、市民ボランティアや研究者など延べ約5,700人が参加し、植物、鳥類、両生類、昆虫などさまざまな生き物のデータを蓄積している。この活動から明らかになったのは、日本の里山環境で身近な生き物たちが急速に減っているという衝撃的な現実だった。特に、日本人なら誰もが馴染みのある「普通種」の減少が顕著に見られた。
例えば、スズメやヒバリといった鳥類、アゲハチョウやシジミチョウといった昆虫など、これまで身近な存在だった生き物が次々と姿を消している。調査では鳥類で年間約3%、チョウでは年間7〜10%も個体数が減少している種があった。これは10〜20年でその数が半減することを意味している。
生息環境別にみると、農地や草原、湿地など開けた場所での減少が目立つ一方で、森林内では生態数が比較的安定していることがわかった。また、鹿やイノシシといった大型獣は逆に増加しており、植生を食い荒らすことで環境全体に悪影響を与えている現状も浮かび上がった。
また、気候変動の影響として、南方系のチョウが北上して分布エリアを広げる一方で、カエルの産卵時期が早まるなど、生態系全体に変化が生じていることもわかった。
虫や小動物が減っている原因は多岐にわたり、農業の縮小や農地放棄によって草地や湿地が減少したこと、都市化の進展、農薬や化学肥料の使用、さらには気候変動など、多くの複合的な要因が重なっていると見られる。特にネオニコチノイド系農薬のような浸透性農薬の影響は、まだデータ上では明確に示されてはいないが、生態系に長期的な負荷を与えている可能性が指摘されている。
さらに「人口が減れば自然が戻る」というイメージは里山には当てはまらず、人が管理をやめた土地は荒れ、外来種や大型獣に占拠され、多様性を失うケースが多い現実も確認された。
虫や小動物の減少は日本に限らず、欧米でも同様の傾向が報告されている。農地や草原に生息する生き物の減少は共通の問題であり、欧州では環境保全型農業を推進するための補助金や制度を整備し、農業と生物多様性を両立させる努力が続けられている。一方、日本ではこうした制度や支援がまだ十分ではなく、農薬や肥料の削減、農地管理の工夫、直接支払制度の見直しなどが急務とされている。
藤田氏は「今回調査を行った場所は比較的良好な環境。それでもこれだけ減少している。調査対象外の地域ではさらに深刻な可能性がある」と警鐘を鳴らす。虫が減っているという実感は、もはや体感や一部の観察者だけの話ではなく、科学的データに裏打ちされた事実となった。虫や小動物は生態系の土台であり、その減少は食物網全体に影響を及ぼす。人間が自然と共生することの重要性とともに、管理することで初めて守れる多様性があることも、この調査は明らかにしている。