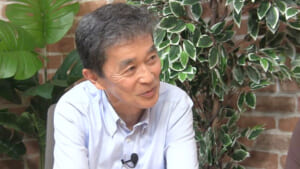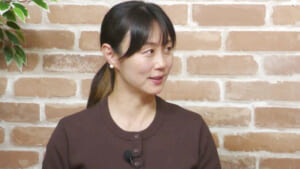新民主党は新自由主義と決別できたことが重要
千葉商科大学准教授


1973年愛知県生まれ。96年明治大学文学部卒業。2009年同大学大学院政治経済学研究科博士課程修了。博士(政治学)。国会議員政策秘書、自然エネルギー財団特任研究員、千葉商科大学准教授などを経て25年より現職。著書に『国会質問制度の研究~質問主意書1890-2007』、『信州はエネルギーシフトする~環境先進国・ドイツをめざす長野県』など。
酷暑で日々人が亡くなっているのに、国政選挙で気候変動が問われないのはなぜだろうか。
7月20日、参議院議員選挙が行われる。しかし、これだけ気候変動の影響が日々の暮らしに現れているにもかかわらず、この選挙で環境・エネルギー政策が大きな争点になっているとは言い難い。各党が環境政策を争点に挙げないのは、環境政策は票にならないと考えられているからだ。もしそれが本当だとすると、これはわれわれ有権者側にも責任があることになる。
果たして各政党は気候危機とどう向き合い、有権者にどのような選択肢を提示しているのか。
第34回の「セーブ・アース」は、環境政策に詳しい千葉商科大学教授の田中信一郎氏をゲストに迎え、各政党の公約における環境エネルギー政策を徹底的に比較・分析する。各党とも通り一遍の環境政策は挙げているが、この番組では政策の字面だけでなく、その背後にある理念や政治的力学、さらには実現可能性までを読み解く。
与党自民党と公明党の公約は、一見して「無難」かつ既存政策の延長線上にある。ネットゼロ、エネルギー安定供給、防災といった文言は並ぶが、その多くは既に政府が取り組んでいる施策の焼き直しに留まっており、現状を変えようという意思は見えてこない。また「原発再稼働」や「新増設」といったデリケートなテーマについては、あえて記述を避けているが、逆に何も言ってないということは、これまでの政策の継続を主張しているということだ。
一方、野党側では立憲民主党の「2050年再エネ100%・原発依存ゼロ」が目を引く。地域分散型のエネルギーシステムへの移行を掲げ、中央集権型の従来モデルとは一線を画すビジョンを提示しているほか、再エネを拡大する中で地域との共生やボトムアップ型の政策設計を重視するなど、前向きな環境政策を打ち出している。しかし、有権者にとっての重要な関心事は、選挙結果次第では立憲民主党が政権の座に就く可能性がある中、ここに挙げられた環境政策の実現可能性にどこまで期待できるかという点になるだろう。
国民民主党や日本維新の会は、原発や火力発電を軸とした「大規模集中型」の電源体制を前提にしつつも、再エネ導入についてはいずれも前向きな姿勢を打ち出している。ただし、両党ともに「次世代原子力」など技術に関して実現可能性に疑問符が付く政策が多いほか、国民民主党については支持母体である電力総連の影響が色濃く反映されている。また、維新の「両取り」路線、つまり再エネも原発も進めるというスタンスは、有権者受けはしそうだが、実際には両者の調整の難しさや制度的矛盾を孕んでいるため、実現可能性という意味では不安が残る。
共産党やれいわ新選組、社民党などのいわゆるミニ政党は、脱原発・再エネ拡大に強い主張を持ちつつも、その主張には財源や技術的裏付けに乏しい部分がある。共産党の「2035年に再エネ8割」という目標、れいわの「原発即時停止」などは、政策としての明快さはあるが、現実的な工程や実現可能性に不安が残る。ただし、省エネ推進や再エネ優先給電などエネルギー政策についての方向性はいずれも一貫している。
ここに来て支持率が急上昇している参政党は、自然環境保護や生物多様性保全などの環境分野には意欲的な姿勢を示す一方で、気候変動については懐疑論の立場に立ち、パリ協定の離脱まで掲げるなど、現在の国際的な科学的コンセンサスからは大きく乖離した政策を主張している。再エネ推進にも否定的であり、その理由に中には陰謀論的な色彩すら感じられる。だが、こうした独自路線が一部有権者層に訴求力を持ち、今後の国政におけるキャスティングボートを握る可能性も否定できない。
こうして各党の政策を比較すると、「再エネ推進」「原発の是非」「地域分散型か集中型か」「脱炭素への本気度」など、いくつもの軸が見えてくる。だが問題は、こうした論点が選挙の中で可視化されず、主要な争点として扱われていないことだ。メディアも連日酷暑のニュースを報じながら、それを気候変動と結びつける報道はほとんどないため、気候問題に対する有権者の関心を深めることに貢献はできていない。メディア報道の至らなさもあって、有権者の多くは「環境は大事」という漠然とした認識はあっても、それを具体的な政策論や投票行動と結びつけることができていないのが現実のようだ。
参院選を前に、各党の環境政策の中身とその評価について、環境政策が専門の田中信一郎氏に環境ジャーナリストの井田徹治とキャスターの新井麻希が聞いた。