たとえ茨の道でも気候危機に立ち向かう1.5度目標を堅持しなければならない 
地球環境戦略研究機関(IGES)気候変動ユニットリサーチディレクター


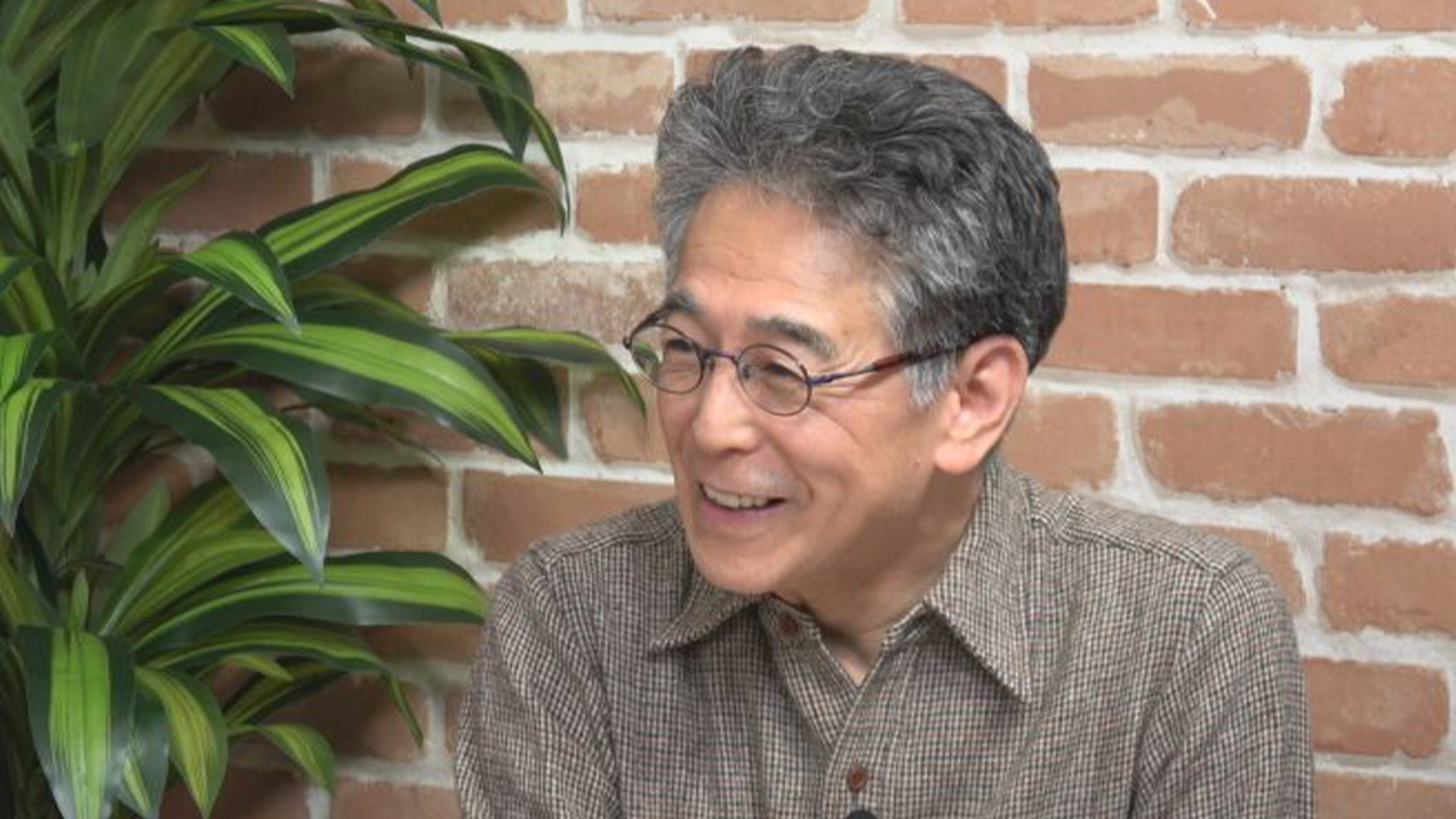
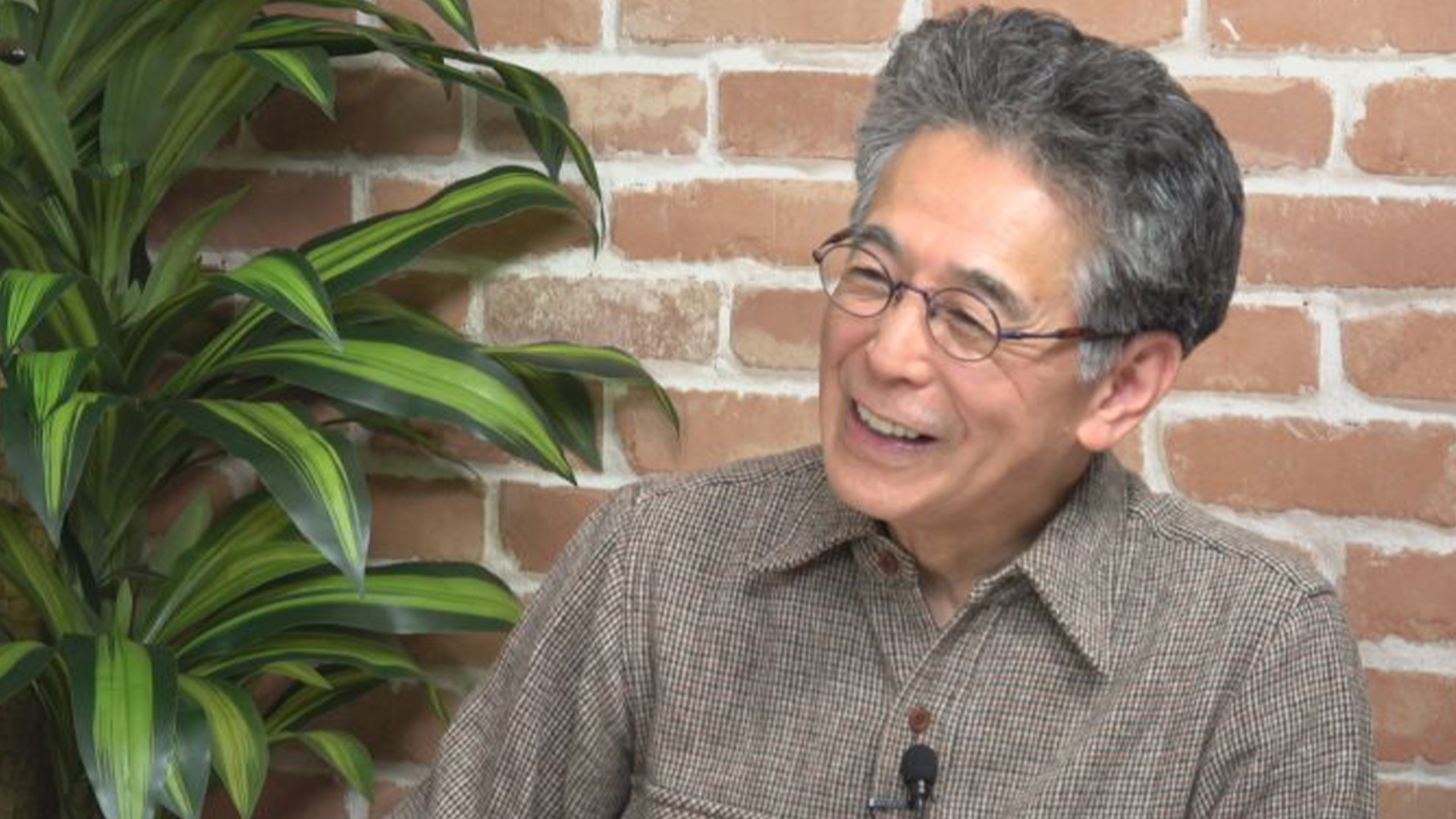
1955年愛知県生まれ。79年東京農工大学農学部卒業。博士(人間科学)。専門は野生動物保全学。83年野生動物保護管理事務所を設立。91年代表取締役社長。2015年退職。立教大学ESD研究所客員研究員、東京農工大学農学府特任教授などを経て、現在は国や自治体の各種鳥獣管理検討委員。著書に『外来動物対策のゆくえ』、『けものが街にやってくる』など。
第38回セーブアースでは、日本各地で深刻化するクマ被害について、最新の研究成果と政策課題を議論した。番組ではクマによる被害報告を始め、クマの生態、森林・農村環境の変容、人間社会の構造的問題、さらには生態系の崩壊が引き起こす連鎖的影響について分析した上で、今後の共存戦略を多面的に提起した。
日本には北海道のヒグマと、本州の広範な山地に分布するツキノワグマの2種類のクマが生息している。野生動物保護管理事務所元代表の羽澄俊裕氏は、近年の特徴として、両者の生息域拡大と行動範囲の広域化があるという。その背景には、温暖化や森林構造の変化などの長期的環境要因に加え、人間活動の縮退という社会変容があると羽澄氏は言う。
クマの個体数の動態は、クマの低繁殖率や広い行動域、高い孤立性といった生物学的特徴によって把握が難しい。特に東北地方から中部山岳にかけて形成される孤立個体群は、遺伝的多様性の低下や局地絶滅のリスクを抱えており、精緻な個体数評価と広域的管理が求められている。近年は、DNA分析を活用したヘアトラップ法などが普及し、従来より高い精度で個体識別や移動解析が可能となっているが、広大な分布域全体で包括的に適用するには、労力・費用・専門人材の面で大きな制約が残ると羽澄氏は指摘する。
羽澄氏はまた、クマの出没が単に山地部の問題にとどまらず、都市近郊にまで広がっている現状は強い危機感を持って受け止める必要があると語る。特に深刻なのは、人慣れしたクマの増加である。過疎化による耕作放棄地の拡大、猟師の高齢化に伴う狩猟圧の低下、さらには都市部と山地をつなぐ緑地空間の増加が、クマを人間生活圏へと誘導しているというのだ。近年では、昼間の住宅街に出没し、自動ドアの仕組みに適応して店舗内へ侵入するなど、クマの行動は人間社会に高度に適応しつつある。
こうした人慣れ個体は、従来の警戒心を喪失しており、遭遇時に攻撃へ転じるリスクが格段に高まる。もはや従来の追い払い手法では対応できず、緊急駆除が不可避となるケースが増えていると羽澄氏は言う。
クマ問題を語る上で欠かせないのが、シカ個体数の爆発的増加による生態系の劣化である。シカが森林下層植生を食い尽くすことで、林床植物群が消失し、日本の森林構造は著しく単純化している。この変化は植物多様性の喪失のみならず、昆虫・鳥類など他生物群にも波及し、生態系全体の機能を低下させている。
植物資源の枯渇はクマの主要食物である堅果類の減少を招き、クマの生活圏を人里へ押し出す要因の1つとなっている。生態系の多段階にわたる連鎖破壊が、クマの肉食性の強化を促し、農畜産物や家屋への接近行動を加速させていると羽澄氏は語る。政府はシカ管理強化のための法制度を段階的に整えているが、現場レベルでの捕獲体制は依然として脆弱で、実効的な個体数削減には至っていない。
今後カギとなるのが、クマと人間の「住み分け(ゾーニング)」だ。クマが定着すべき山地や森林と、人間社会が活動する市街地や農地を地理的、構造的に区分することで、不必要な接触を抑制する必要がある。河川敷や郊外の緑道は、野生動物の移動経路となりやすく、重点管理区域とすべきだと羽澄氏は言う。
羽澄氏はまた、人材不足が野生動物管理の根本的な弱点となっている現状も指摘する。狩猟者の高齢化が進む中、若手の育成は急務であり、専門的な訓練を受けた「ガバメントハンター」制度の整備が不可欠だという。加えて、出没時の初動対応では、自治体、警察、自衛隊の連携体制を平時から構築しておく必要があるという。
クマ被害は単一の現象ではなく、生態系変動や社会縮退、行政体制の制約が重層的に絡む構造問題であると語る羽澄氏と、クマ出没の常態化が持つクマ側の事情と人間側の要因について、環境ジャーナリストの井田徹治、キャスターの新井麻希が議論した。


