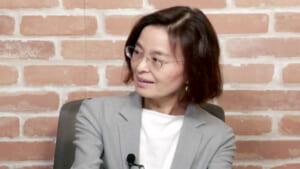人々の生活や自然を破壊する過度な再エネ開発は間違っている
弁護士


1955年山口県生まれ。78年九州大学工学部卒業。80年九州大学大学院工学研究科修士課程修了。博士(工学)。専門は河川工学、河川環境。80年建設省(現国土交通省)入省。土木研究所研究員、九州地方整備局武雄河川事務所長などを経て2003年より九州大学工学研究院教授。21年、定年退職し現職。著書に『協働による環境と防災の調和』、編著に『河川災害と復興』など。
五島列島のいちばん北にある小さな島で、いま日本最大規模と言われるメガソーラーの建設が始まっている。
美しい海に囲まれた宇久島は、平成の大合併で長崎県佐世保市の一部となったが、今も人口減少が進んでいる。事業面積が島の4分の1を占めることになるメガソーラーの開発は雇用創出などの地域振興も目的として掲げられているが、島の自然環境を損なう恐れがあるとの理由で、地元から反対の声が上がっている。
そもそもこの島でメガソーラーの話が始まったのは、再生可能エネルギー(再エネ)の固定価格買取制度が導入された2012年のことだった。ドイツの企業がFIT(固定価格買取)制度を利用してキロワットあたり40円の買取価格で認定を受け、それを引き継いだ日本企業が事業を進めている。完成した場合、発電能力は480メガワットとなり、年間発電量は17万3,000世帯分の使用量に相当する。人口約1,700人の宇久島にとっては、自分たちのためではなく、本土に送られて使われるための電力開発となる。
発電容量1メガワット以上というメガソーラーが環境にどれほどのダメージを与えるのかは、まだよくはわかっていない。
治水の専門家として宇久島のメガソーラー開発の現場を視察した熊本県立大学共通教育センター特別教授の島谷幸宏氏は、水の循環という観点から島全体の調査が必要だと指摘する。森林を伐採した後にソーラーパネルが敷き詰められることで、気象の変化や、洪水量の増加、地下水の減少など、生態系全体に関わるさまざまな事態が想定される。ヒートアイランド現象のような都市化による水循環の変化と似たような現象が起こる可能性もある。こうした環境への負荷をどう緩和したらよいのか。そもそも緩和は可能なのか。手遅れにならないうちに環境負荷を最小限に抑える方法を考えなくてはならないと島谷氏は強く訴える。
太陽光発電を巡っては、すでに全国各地でトラブルが起きている。去年3月に総務省が発表した資料では、回答した自治体の4割を超える355市町村で、太陽光発電関連のトラブルが発生しているという。その中身は土砂災害が復旧されない、土砂災害発生の懸念がある、土地開発部局の許可を得ていないなどさまざまだ。
こうした問題に早い段階から警鐘を鳴らしている日弁連のメガソーラー問題検討プロジェクトチームは、法律による規制と並行して、地方自治体が地域に即した条例を制定することを推奨している。河川工事や水害後の災害復旧で住民参加の取り組みの経験を多く持つ島谷氏は、集落ごとに議論を繰り返し、暮らしを守りながら合意形成の道を探るしかないと語る。
先月、政府が閣議決定した新たなエネルギー基本計画では、2040年度の時点で再エネのシェアを4割~5割まで増やし最大の電源にすることが謳われている。それを受けて今後、再エネの導入はますます進むことが予想される。安全面、防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄などの観点から、本気で地域との共生を考えなくてはならない時が来ている。
自然を護りながら再エネのシェアを増やすためにはどうすればいいのか。河川工学と治水の立場からこの問題に取り組む島谷幸宏氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。