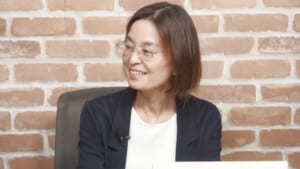「社会保障は重すぎる」は本当か 
慶應義塾大学商学部教授




1948年長野県生まれ。73年東京大学法学部卒業。同年厚生省(現・厚生労働省)入省。老人福祉課長、年金課長、老健局長、社会・援護局長などを経て2008年退官。08~10年、社会保険診療報酬支払基金理事長。10年~14年、内閣官房社会保障改革担当室長(「社会保障と税の一体改革」担当)。12年、医療介護福祉政策研究フォーラムを起ち上げ理事長に就任。同年より国際医療福祉大学大学院教授を兼務。著書に『平成の社会保障』、『2001−2017年 ドキュメント社会保障改革』など。
年金制度改正法案が5月16日、ようやく政府から国会に提出された。
法案には厚生年金への加入対象を拡大し、いわゆる106万円の壁をなくすことや、年金を受給しながら働く高齢者が増えるよう在職老齢年金の基準の引き上げなどの改正は盛り込まれたが、最も大きな争点となっていた基礎年金の底上げは先送りされた。
年金制度は5年ごとの財政検証で経済の状況や支え手の減少、受給者の増加など将来の見通しを立てた上で、適正な給付水準を算出することになっている。
2024年7月時点で厚労省が発表した数字では、基礎年金の水準が現時点より3割ほど下がる可能性が指摘されていたが、その問題への対策は今回の法案には盛り込まれていない。
公的年金は、国民全員が加入する基礎年金部分と企業などで働くサラリーマンが加入する厚生年金の報酬比例部分の2階建てとなっている。基礎年金のみを受給するいわゆる国民年金の対象者は、自営業や農業、専業主婦などだ。国民年金は積立金が少なく財政基盤が弱いため、厚生年金の積立金を基礎年金部分により多く配分することで基礎年金の給付水準を底上げする案が検討されていた。
野党は基礎年金の底上げが先送りされたことに一斉に反発している。中でも立憲民主党は修正案の骨子を示し、与党と修正協議を始めている。
与党がなぜ基礎年金の底上げを法案に盛り込まなかったのかについて、元厚労省の官僚で退官後に「社会保障と税の一体改革」に携わった中村秀一氏は、年金問題が政権交代の引き金になった過去の経験がトラウマになっているのではないかと語る。
2009年の総選挙では、消えた年金問題など年金が大きな政治問題となったことが、自民党大敗の一因となったと考えられている。
そもそも年金制度は制度そのものが複雑だ。今回の財政検証にしても、2004年の年金制度改正で盛り込まれたマクロ経済スライドという仕組みを使って調整を行い、物価や賃金上昇率より年金額の上昇率を抑制した結果、基礎年金の水準が下がることになったと説明されているが、その説明を理解し、ましてやそれに納得している人が、果たしてどれほどいるだろうか。保険料の上限を固定して概ね100年間で財政均衡を図るという条件のもとで計算した結果、そうなるのだそうだが。
長い年月をかけて積み立てられている年金制度の改革は、短期間で実現できるものではない。中村氏が厚生省年金課長時代に担当した年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるという制度改正も、1994年から段階的に引き上げて今年やっと男性の支給開始年齢を65歳に揃えることができたところだという。
今回、立憲民主党の修正案を与党が受け入れるとしても、元の政府案より改革時期が遅れることは確実で、しかも就職氷河期世代で非正規の仕事が続いて基礎年金しか頼ることができない人たちの老後の生活を保障する金額にはとても満たない。
いずれにしても目先の損得だけに囚われず将来世代のことまで視野に入れた上で、年金制度が必要としている改革を実現するためには、国民への丁寧な説明が不可欠で、それは政治の責任だ。
政府が提出した年金改革案の評価と問題点、そして公正な公的年金とはどうあるべきかなどについて、民主党政権から第二次安倍政権にかけて内閣官房社会保障改革担当室長を務めた中村秀一氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。