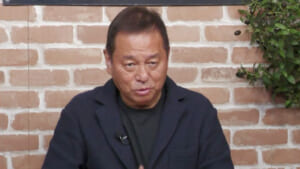「減反廃止」で日本の農業は生き残れるか 
東京大学大学院農学生命科学研究科准教授




1986年島根県生まれ。2009年東京農工大学農学部卒業。17年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。専門は農業経済学、農政学、人間科学。23年より現職。東京農工大学大学院連合農学研究科助教、公益財団法人日本農業研究所客員研究員、一般財団法人農政調査委員会専門調査員などを兼務。著書に『日本のコメ問題』、『現代日本農業論考』など。
コメの値段が高騰している。スーパーで販売されている5kgあたりの精米の平均価格は4,214円と、1年前の2倍以上に跳ね上がっている。
これまでコメはいくらでも安く買えて当たり前な、いわば空気や水のような存在だったため、われわれはコメやコメ市場に何が起きているのかについてやや無関心過ぎたのではないか。今回のコメ価格の高騰を奇貨として、日本人の食生活に欠かすことのできないコメに今何が起きているのかを議論した。
コメは2023年の夏前の日照不足と夏場の猛暑によって1等米の収量が大きく下がる一方で、コロナ明けのインバウンド需要や外食産業の需要が急回復したことで、全般的に品薄状態が続いていた。
宇都宮大学農学部の小川真如助教は、2024年末からの価格高騰の背景には品薄になったコメを巡る業者間の集荷競争があったと指摘する。コメ農家はより高い価格を提示した業者にコメを渡すため、集荷競争が起こると必然的に価格はつり上がる。コメが品薄になったタイミングで南海トラフ地震への注意を呼びかける臨時情報が広く発表されたことで、昨年末から今年初めにかけて集荷競争が更に激化し、小売価格が高騰したのだという。
そのような一時的な要因で米の価格が上がっているのであれば、早晩その価格は元に戻っていくかもしれない。しかし、小川氏は、日本のコメは「田んぼ余り」という構造的な問題を抱えており、今後コメの価格が下がったとしても、その問題が解決するわけではない点は注意が必要だと言う。
戦後の食料不足を乗り切るため、日本は食管法の下で国が農家から買い取ったコメを安く国民に供給する体制を整備した結果、1967年にはコメの自給が達成された。しかし、自給が達成された瞬間に、コメ余りが始まった。国が買い上げたコメが売れ残れば、自ずと国の財政負担は増える。
そこで政府は1978年から本格的に減反政策を始め、コメの生産量を削減したり、麦や大豆などに転作した農家に対して補助金を出すようになった。その結果、国内ではコメを作らない田んぼが増えていった。
1993年にはGATTウルグアイラウンドが妥結し、コメについても徐々に市場メカニズムが導入されることとなったが、田んぼについては「食料安全保障」や「洪水防止機能」などを理由に、政府による保護が続いた。
今はたまたまコメ不足が問題となっているが、小川氏はむしろ日本の問題は、コメ余りへの対応が考えられていないことだと言う。これまで政府はコメが不足した場合を想定してさまざまな対応策を打ってきたが、コメが余った場合については十分に考えられてこなかった。減反はコメが不足もしないし過剰にもならない状態を維持するための政策だが、そこには余ったときにどうするかという発想はない。減反によってほどほどにコメが足りている状態を作ろうとすると、気候や外的要因など何らかのストレスが加わると、たちまちコメ不足に陥ってしまう。むしろこれからのコメ政策は、余った場合を想定して、輸出の推進など多角的な方策を考えていかなければならないと小川氏は指摘する。
さらに小川氏は、人口減少によって日本の食料安全保障のために必要な農地の面積が実際の農地面積を下回り、田んぼだけでなく農地全般が余る時代が来ることが予想されると指摘する。田んぼ余りの轍を踏まないためにも、余った農地をどうするのかを今のうちに考えておく必要があると小川氏は言う。
今回のコメ価格高騰の背景には何があるのか。日本のコメが抱えるより本質的な構造問題とは何か。コメの安定供給を実現するためにはどうすればいいのかなどについて、宇都宮大学農学部の小川真如助教と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。