福島原発事故の原因はまだ判明していない 
元国会事故調委員・科学ジャーナリスト
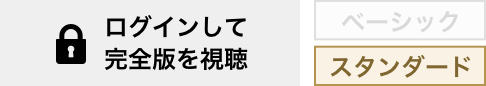
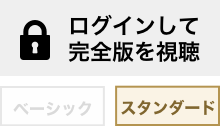
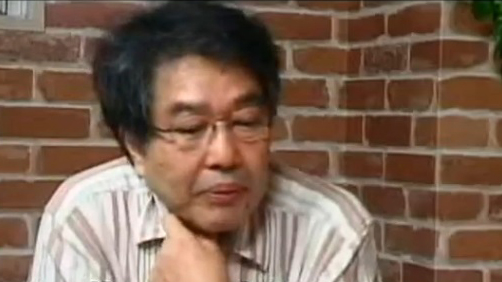
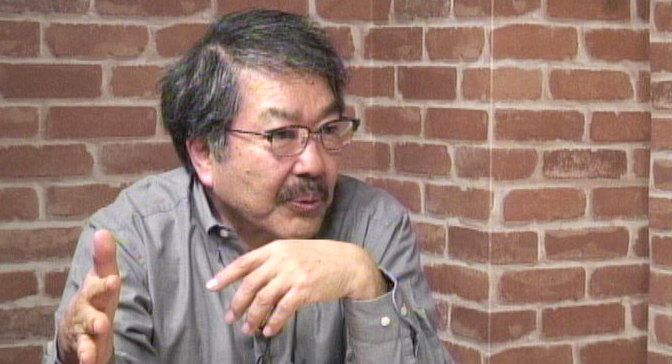
1943年栃木県生まれ。68年東京工業大学工学部卒業。同年バブコック日立入社。77年退社、同年より科学ジャーナリスト。2011年東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)委員。13年4月より新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会委員。著書に『原発はなぜ危険か・元設計技師の証言』、共著・訳書に『複雑系の選択』、『デカルトの誤り・情動、理性、人間の脳』など。
7月16日の新潟中越沖地震で、東京電力柏崎刈羽原発は大きく損傷を受けた、今回は幸い放射能漏れなどの大事故にはいたらなかったとされているが、それはあくまで「たまたまそうだった」という結果論に過ぎない。東京電力は今回の地震が、原発の耐震強度が想定されていた地震の規模を大きく超えるものだったことを認めている。実際には何が起きていてもおかしくなかった。
しかし、それにしても地震大国の日本で、いまさら「想定されていなかった」とはどういうことなのだろうか。確かに新潟中越沖地震は人的被害も出るほどの強い地震だったかもしれないが、しかしそれは決して前代未聞の大地震ではなかったはずだ。
原子炉の設計を行っていた田中三彦氏は、もともと日本の原発には耐震性という概念自体が1978年に耐震設計審査指針が策定されるまで、存在しなかったという。それ以前に認可を受けた原発は、耐震性能はメーカーの自主基準に基づいているに過ぎないのが実情だ。田中氏によると、本来原発の安全性を担保している電力会社、原発メーカー、行政の3者は、いずれも耐震性について十分な知見は持っていない。ある程度以上の地震が原発を直撃した場合、本当に何が起きるかは実は誰もわかっていないというのだ。
元原発設計技術者の田中氏に、日本の原発の地震対策の実情を聞いた。
また、安倍首相の辞任と後継総裁選びをめぐる自民党内の動きを、政治ジャーナリストの上杉隆氏に電話で聞いた。