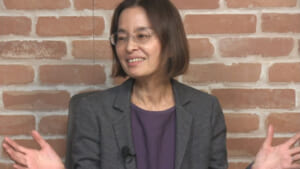被災地の前市長が語る「現場感覚のない政治に危機管理はできない」 
元南相馬市長




1956年福島県生まれ。78年岩手大学農学部卒業。2003年、原町市議会(06年より南相馬市議会)議員初当選(2期)。10年、南相馬市長初当選(2期)。22年より現職。
大津波と原発事故の二重災害を引き起こした東日本大震災から、この3月で12年がたつ。
原発被災地でも避難指示区域の解除が進み、今も帰還困難区域に指定されるのは福島第一原発の立地自治体だった双葉町と大熊町のほかは、浪江町、飯舘村、南相馬市、葛尾村、富岡町の一部となった。双葉町と大熊町の中にも部分的に避難指示を解除して居住が可能な「特定復興再生拠点」が設けられ、少しずつ人が戻り始めている。とはいえ大熊町と双葉町の現在の人口は震災前と比べるとそれぞれ4%、0.7%に過ぎない。
なかなか人口が回復しない中、いかにしてまちを再建させていくのか。当時、原発被災地の首長の一人として最前線で対応にあたった前南相馬市長の桜井勝延氏は、震災前に7万1,000人余りあった南相馬市の人口が、震災後に8,500人まで激減したあと、翌年には5万人近くまで回復したものの、その後はほぼ横ばいが続いているという。なんとか戻ってもらいたいと市民と対話を続けてみたが、特に避難先での生活が定着してしまった若い世代に帰還してもらうのが難しいことがわかり、今は発想を変えて、いかに故郷との関係を維持してもらうかに腐心しているという。
南相馬市は2006年に平成の大合併で3つの地区が合併してできた市だ。その3つの地区が、それぞれ原発から20キロ圏内、30キロ圏内、30キロ圏外と分かれているため、市民の意識をまとめるのが難しい。国の政策がかえって人々を分断していくなかで、市政は難しい舵取りを迫られた。そのような地方自治体の苦悩はほとんど伝えられておらず、原発被災地の実情はますます分かりにくくなっている。
そのような難しい状況の下にあっても、南相馬市は国の支援制度を活用して、産業の復興に努めてきた。除染や災害公営住宅の建設などで、ピーク時には1,200億円まで膨れあがった南相馬市の予算は徐々に通常の状態に戻りつつある。製造品の出荷額は震災前のレベルに戻ったが、農業は圃場整備を進めてはいるもののまだ震災前の4割程度だという。
国の支援を受けながら12年間、復興のために走り続けてきたが、これから先、どのようなまちづくりをするかをめぐる課題は多い。当初は、国や事故を起こした東京電力に対する市民の怒りが大きなエネルギー源となっていたが、時間がたつにつれその感覚が薄れてきた結果、多くの市民がもはや諦めの境地に入っている感があると桜井氏は言う。南相馬市の復興を牽引してきた桜井氏自身、2018年に3期目を目指して市長選に出馬したものの、現市長の門馬和夫氏に敗れてしまった。今は市議会議員の立場から、市の今後を考える立場にある。
12年という時の流れの中で原発被災地の現状をどう捉えたらよいのか。南相馬市議会議員の桜井氏と社会学者の宮台真司氏とジャーナリストの迫田朋子が議論した。