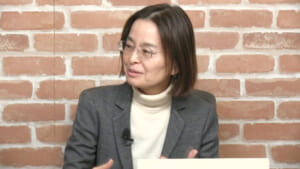日本人の行動を支配する「空気」の正体とそれに抗うための方策 
大阪大学大学院人間科学研究科准教授


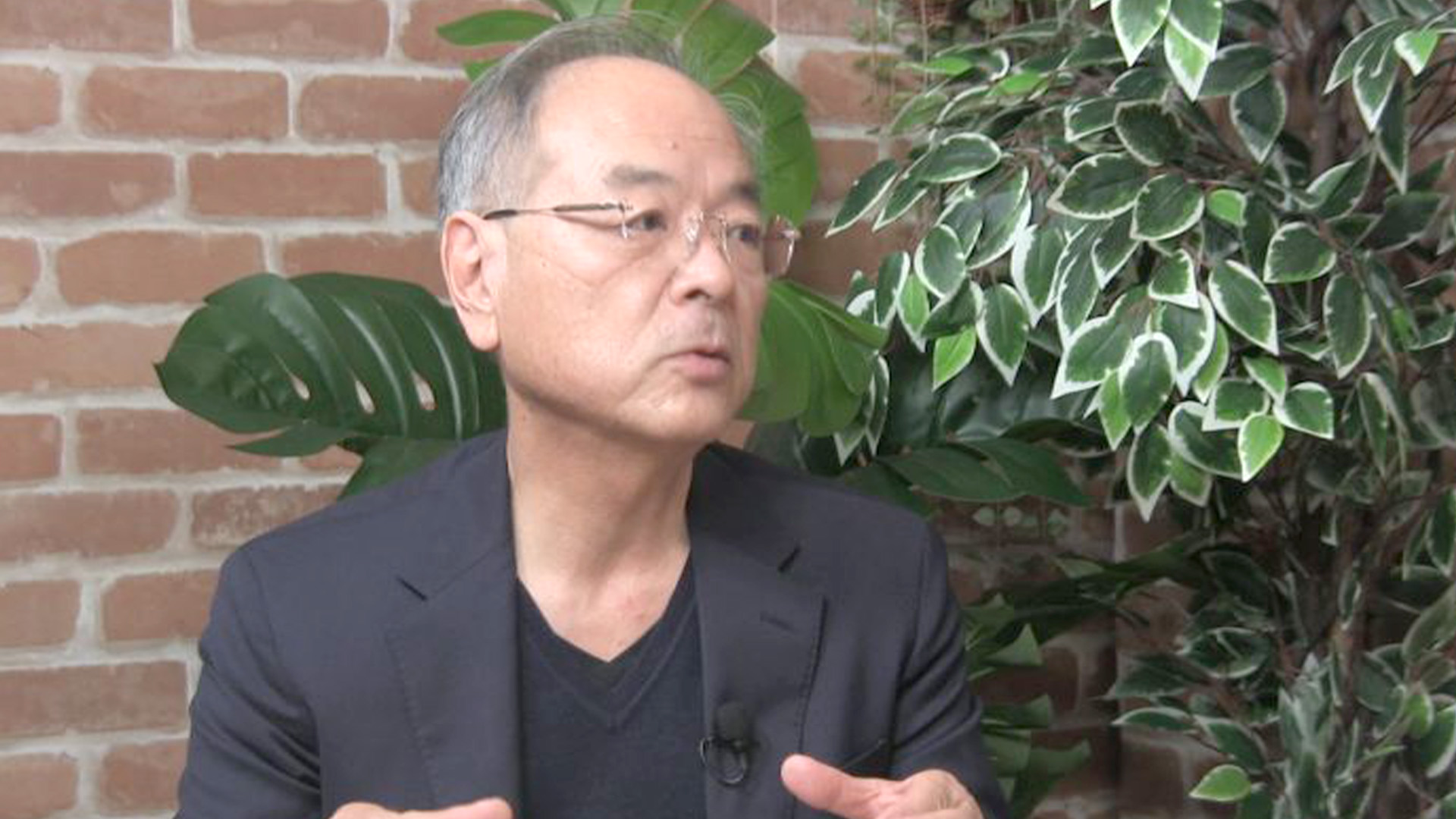
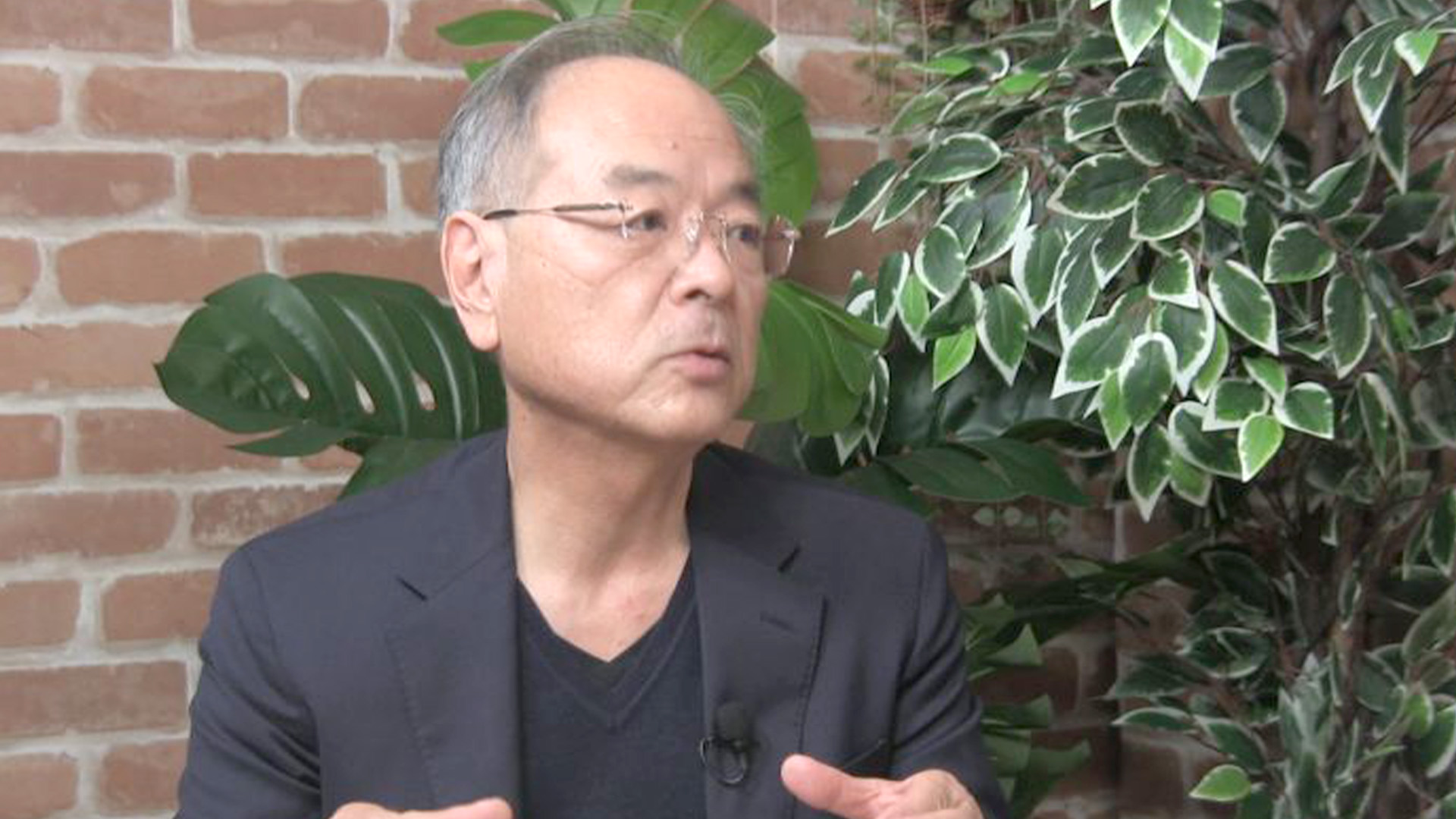
1955年兵庫県生まれ。78年関西学院大学社会学部卒業。82年トロント大学ソーシャルワーク修士(MSW)、94年同大学Ph.D.取得。専門は福祉防災学、家族研究、市民社会論。関西学院大学社会学部助教授、同教授を経て2001年より現職。著書に『災害と復興の社会学』、『誰一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべきこと』など。
6,000人を超える犠牲者を出した阪神・淡路大震災から30年目を迎えるこの1月、石破政権の重要施策である防災庁設置に向けて有識者会議が発足し、具体的な議論が始まる。
果たしてこの30年で日本の防災対応力は向上したのか。
この30年の間にも、東日本大震災、熊本地震や昨年1月の能登半島地震など、日本は幾多もの災害に見舞われてきた。災害が起こるたびに新たな対策が取られてきたが、厳しい避難生活や災害関連死の増加など、震災の度に明らかになる諸課題を中々解決できないでいる。
現政権が重点的に取り組むとしている避難所環境や備蓄体制の改善などは、誰も異存のないことだろう。ただ、震災対策としてはそれだけでは十分ではないことも、この30年の経験から学んできているはずだ。
災害関連死は、30年前の阪神・淡路大震災当時から指摘されてきたが、能登の被災地では状況がより過酷になっていると福祉防災学が専門の同志社大学教授・立木茂雄氏は指摘する。最大避難者数と災害関連死発生率をグラフにすると緩やかな上昇カーブになるのだが、東日本大震災の福島県と能登半島地震はその曲線から関連死発生率が極端に上振れしているという。奥能登地域では停電、断水が長く続き、保健や福祉の専門職などの支援が十分に届かず、被災者は過酷な避難生活に追い込まれた。
能登半島をはじめ多くの被災地に足を運んできた立木氏は、災害によって被災地の状況が大きく異なることを指摘する。過去の災害からの経験則だけでは対応できないため、その都度知恵を働かせなくてはならないのだ。生産年齢人口がピークを迎えた1995年に起きた阪神・淡路大震災と、高齢化率が50%を超える能登半島で起きた地震とは、見えている事象が同じでも復旧・復興にむけての過程は大きく異なる。
立木氏は、防災庁設置に向けた方針としてあげられている「復旧・復興の司令塔機能の強化」という表現に疑問を投げかけ、災害対策で必要とされるのは一にも二にも調整機能だと主張する。阪神・淡路大震災後にできたDMAT(災害派遣医療チーム)をはじめ、さまざまな支援の仕組みがありながら多くの人が取り残されるのは、被災自治体や住民、支援チームなどの間でコーディネーション(調整)ができていないからだというのだ。
30年前、西宮の自宅で被災した立木氏は、当時勤務していた関西学院大学の学生や教員たちとボランティアの仕組みをつくり支援を続けた経験を持つ。当時、こうした活動は「ボランティア元年」などとして盛んにメディアで取り上げられたが、震災時の市民セクターの活動の原点は、100年余り前の関東大震災後の活動にあったと立木氏は言う。その後、太平洋戦争を経て、戦後の国づくりは政府・企業という大きなセクターを中心に進められたが、あらためて市民の力が再認識されたのが阪神・淡路大震災だったと立木氏は語る。
政府や行政機関が好んで使う「官民連携」という言葉も、本来のボランタリズム精神の前提にある市民側からの自主的で対等な関係を意味しているのか疑問が残る。
阪神・淡路大震災から30年目を迎える中、日本では再び大きな災害の発生が予想されている。今あらためて災害対応力とは何なのか、生活再建に必要なことは何なのかなどについて、福祉防災学の専門家として調査・研究を続けてきた立木茂雄氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。