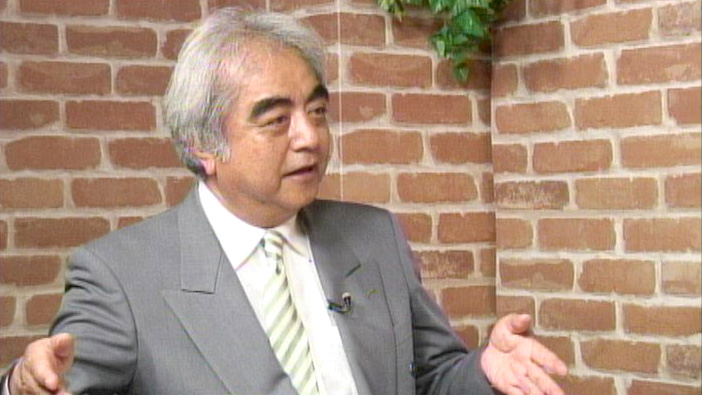
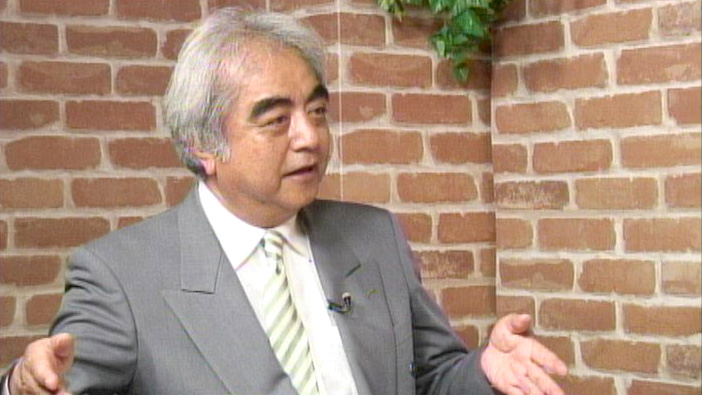
1954年北海道生まれ。77年立教大学社会学部卒業。同年航空ジャーナル社に入社。『月刊航空ジャーナル』編集長などを経て88年より現職。著書に『飛行機事故はなぜなくならないのか』、『事故調査報告書が語る航空事故の真実』など。
あれから30年、世界の空はより安全になったのだろうか。
1985年8月12日、日本航空123便が御巣鷹の尾根に墜落し、乗員乗客520人が亡くなるという単独事故としては航空史上最悪の事故が発生した。
その後行われた航空機事故調査委員会(事故調)の調査で、123便は1978年の尻もち事故後の機体後部にある圧力隔壁の修理に不備があり、飛行中に隔壁が損壊したことで垂直尾翼や操縦系統が破壊され、操縦不能に陥り墜落したとされた。
航空機のメカニズムや航空機事故に詳しい航空ジャーナリストの青木謙知氏は、航空機事故の原因を100%正確に掴むことは困難だが、機体の残骸やフライトレコーダーなどの記録をもとに、当時の事故調の調査は妥当なものだったと評価する。しかし、その一方で、相模湾上を飛行中に吹き飛ばされたとされる圧力隔壁の上半分が回収されなかったことから、高い強度を持つよう設計されている垂直尾翼が、いかに破壊されたかについては十分な解明ができているとは言えないなど、30年が過ぎても十分に解明されたとは言えない点が残っていることも事実だ。
海外の航空機事故の調査では海に落ちた機体の残骸なども回収され、徹底的な原因究明が行われるのが普通だという。この点で当時の日本では政府もメディアも、事故原因やそのメカニズム究明の重要性に対する認識がやや甘かったのではないかと、青木氏は自戒の念を込めて振り返る。また日本の事故調の調査には法的強制力がないため、事故原因の究明につながる証拠をすべて押収することが難しいこともあり、同時進行で刑事責任の追及が行われる場合が多い。それが結果的に、関係者から事故調の調査に対する全面的な協力を取り付けることを困難にするなど、事故原因の究明には制度上の障害もある。30年前の事故当時から指摘されてきた問題だが、今も基本的にこの状況に変わりはない。
30年前の事故は、仮に原因が事故調の結論通りだとしても、なぜ修理ミスが起きたのか、なぜそれが検査で発見されなかったのかなど、依然として不明な点も多い。青木氏は検査の最終確認をする立場にある当時の運輸省(現国土交通省)に航空機の修理を細部まで適正に評価する能力が備わっていないため、修理は事実上日本航空に丸投げの状態にあり、その日本航空も実際の作業はボーイング社のエンジニアに任せっきりだったところに問題があったと指摘する。
また、昨今の原発問題にも通底する話だが、当時、航空機、とりわけジャンボ機はフェイルセーフが確立されているので決して墜落することはないといった安全神話がしきりと喧伝されていた。そのため、「絶対安全なのだから」という過信が、修理後の厳しいチェック体制の整備を困難にすると同時に、担当者や担当部局の責任回避に繋がっていったという青木氏の指摘は重い。
とは言え、油圧系統が機体後部で一箇所に集中するという、30年前の事故で露呈した構造上の弱点は、その後ボーイングによって改善が図られるなど、事故後、航空機の安全性が大きく進歩したことはまちがいないと青木氏は言う。また、航空機事故の事故率(100万飛行当たりの事故発生件数)も、1986年の1.73から2013年の0.55まで、3分の1以下まで大きく減少している。総じて航空機の安全性は高まっていると考えてよさそうだ。
しかし、それでも高速で空を飛ぶ航空機は、一旦事故が起きると、取り返しのつかない重大な事故になることが避けられない。青木氏はハイテクの導入によって航空機の安全性が高まったことは事実だが、その一方で、事故が完全に無くなることはないと指摘する。それは、システムが複雑化すればするほど、常に想定外のトラブルや新たな問題が出てくるからだ。
また、メカニカルトラブル以外にも航空機の安全を脅かす要素はある。今年3月、乗客乗員150人を乗せたドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機がフランスで墜落した事故では、副操縦士が、故意に高度を下げる装置を作動させ、墜落させたとみられている。どんなに技術が進歩しても、ヒューマンエラーによる事故や、故意による事故を100%防ぐことは容易ではないだろう。
日航機墜落事故から30年、果たして世界の空はより安全になったのか。事故が残した教訓や現代の航空技術の進歩、新たに出てきた問題などについて、ゲストの青木謙知氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。